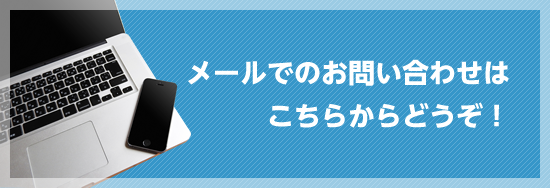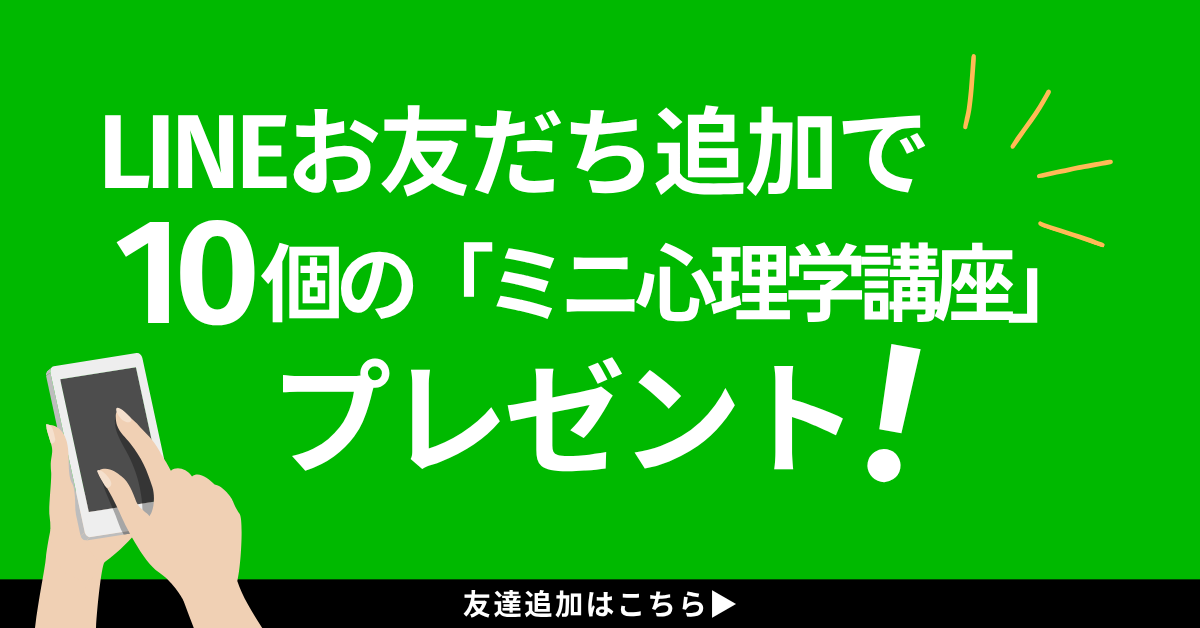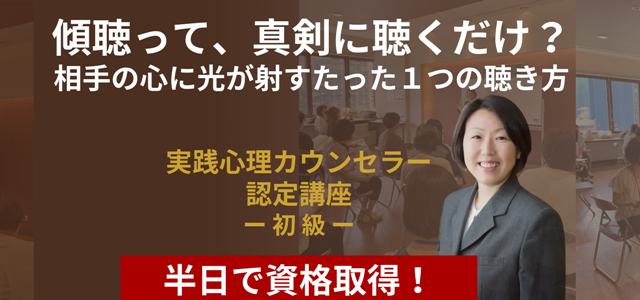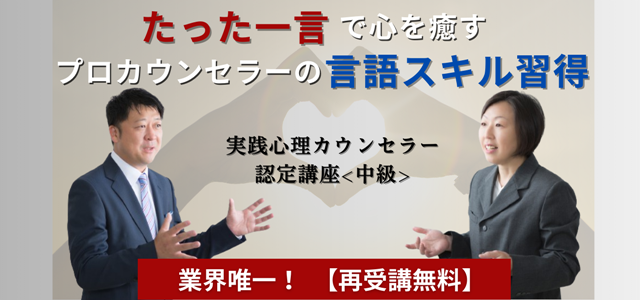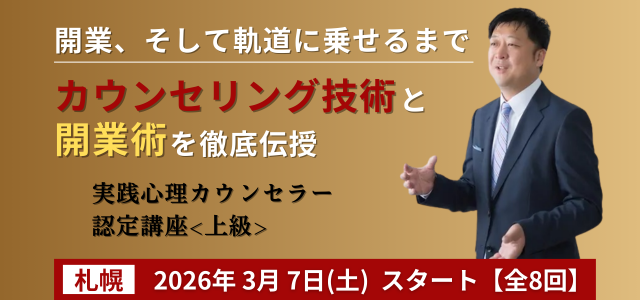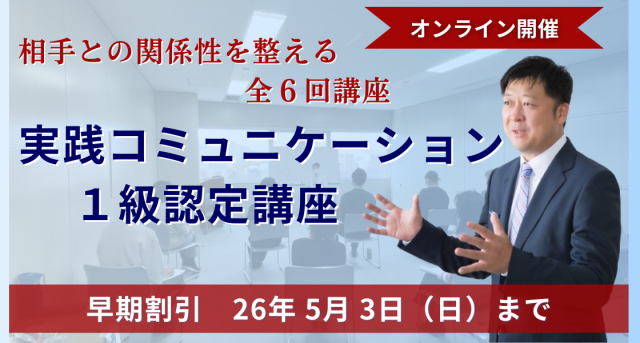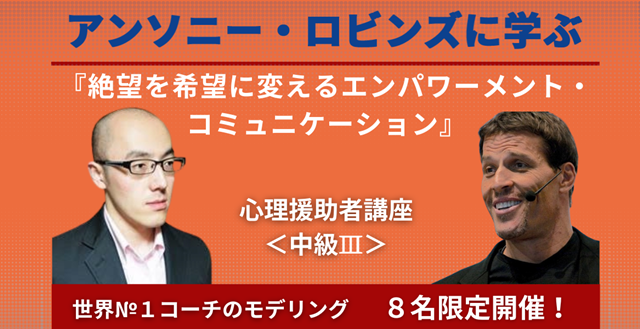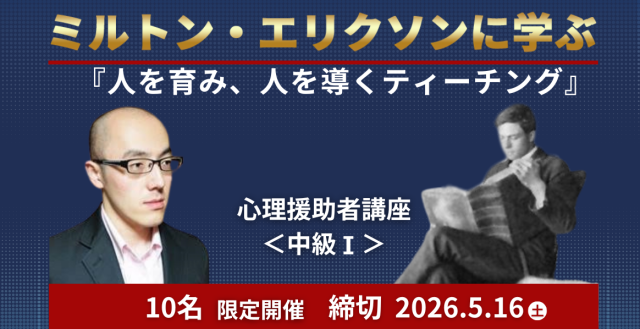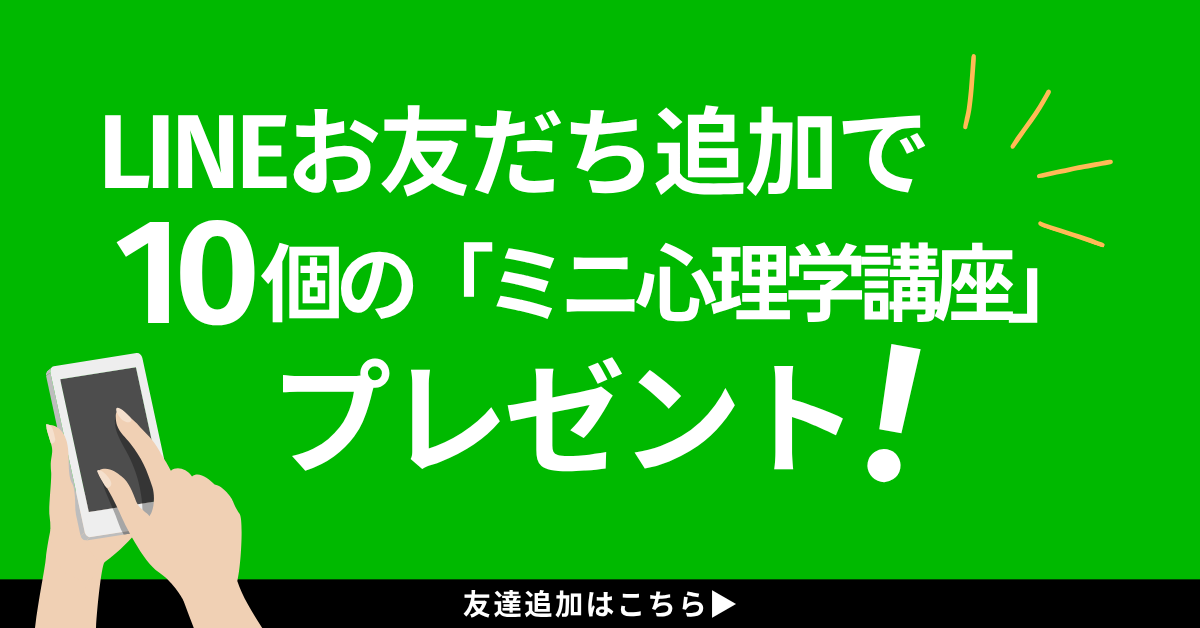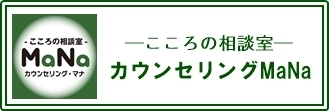男女心理学
「余計なことばかりする夫」「ダメ出しばかりする妻」②

2022/6/4
「見なかったことにしよう…」
すっかり乾いた洗濯物が風に揺られているのを見た瞬間、そう思いました。
それくらい、その日はやることに追われ余裕がなかったのです。
「余裕のある方が洗濯物を取り込み、たたむ」
それが自然と私たち夫婦のルールとなっています。
ですから、私が洗濯物を取り込まなくても、妻は何も文句は言わないはずです。
その日(その日どころか連日)、私に余裕がないのは妻もわかっていますから。
「でも、待てよ。これだけ忙しいにもかかわらず洗濯物を取り込んだら…」
ふとそんな考えが浮かびました。
すると、喜びと、感謝でいっぱいになる妻が浮かんできます。
「うわー、こんなに忙しいのにありがとう。助かるー!!」という妻が。
考えてみたら、妻だって忙しいのです。
洗濯物をたたみながら、世の妻の不平のからくりが見えてきた気がしました。
- 「うちの夫、全然手伝ってくれないんです」
- 「『子ども見てて』と頼むと、本当に見ているだけ…」
- 「手伝ってるつもりらしいけど、全然手伝いになっていない!」
という不平のからくりが。
妻の不平の具体例はこちら
<関連記事> 余計なことばかりする夫、ダメ出しばかりする妻①
おそらく、世の妻は、そっけないのでしょう。
せっかく夫が、「妻が喜んでくれるかな?」と思って手伝う。
なのに、妻はあまり褒めない。
「あぁ、ありがと…」と気のない返事しかしてくれない(そして、ときには「そうじゃないでしょ!」のお叱りが来る)。
だから夫は手伝わなくなる。
「よし、今度このことをHPの記事にしよう。妻が喜んでくれる顔、妻の感謝している声。
それが夫が家事を手伝うヤル気を引き出します。だから、妻の皆さん、伝え方に気をつけましょう」と。
ところが、そう思った瞬間、疑問がわきました。
本当にそうなのか?
本当に、世の妻の、喜びや感謝の伝え方が問題なのか?
もしそうなら、世の妻は、喜びと感謝をオーバーに伝えなければならないのでしょうか。

整理してみましょう。
- 家事を手伝い、(暗に)感謝を求める夫
- 家事を手伝われて、(うわべの)感謝を伝える妻
この構図のどこに問題があるのか。
私は、はじめ、妻の伝え方に問題があると考えました。
ですから、妻が大げさにでも夫に感謝を伝えればよい、と。
でも、もしそうしなけばならないのなら、妻側は苦しいのです。
感謝する気持ちが起きないのに、
「ありがとう♪」
と、いかにも喜んでいるように伝えるのは。
これは、想像以上に苦しいことです。
思っていることと、口にする言葉が違うから(自己不一致)。
実際、やってみればわかることです(おすすめはしませんが)。
感謝を伝える際に、頬や口元に、ひきつったような無理な力がかかります。
口から出る声も、喉に引っかかるような感覚になります。
声を出した後も、胸のあたりに何とも重苦しい感覚がしていることでしょう。
それくらい、感謝していないのに感謝しているフリをするのは苦しいことなのです。
そして、残念ながら、言われる夫側も苦しい。
「あれ? そんなに嬉しそうじゃない…」
妻の思いを不自然な非言語から感じてしまいますから。
せっかく喜んでもらえると思ったのに、よそよそしい態度の妻。
かえって、二人の間の距離を意識させてしまうことにもなりかねません。
ですから、妻の伝え方に問題があるわけではない。
無理に感謝を妻が伝えても、お互いが苦しくなるだけです。
まさに、がんばってはいるのにうまくいかないというパターンに陥ります。
そして、実際にはこのように、夫も妻も、どちらもがんばっているのに苦しくなっている。
そんな事例が多いのが実態なのです。
では、いったい、何が問題なのでしょうか?

その問題とは、妻がそもそも感謝できていないことです。
せっかく夫が手伝ってくれたのに、ありがたいと思わない。
それこそが、問題の本質なわけです。
それでは、どうして妻は感謝できないのか?
性格が悪いのでしょうか。
いえいえ、そうではありません。
ここでカギになるのが、男女の違い。
女性が持っていて、男性にはない機能。
<母性の門番>という機能です。

誰かに物事を任せるとき、二つのパターンに分かれます。
①結果を重視
②過程を重視
たとえば、会議で使う資料の配布を頼む場合。
①であれば、とにかく会議のときに、全員の手元に資料があればよいわけです。
印刷物がホチキスで留めてあろうがクリップだろうが、配布したのが前日だろうが、当日だろうが、どちらでもよい。
何なら、会議のときに配布してもよい。
会議のときに全員の手元に資料がある(結果)のが重要。
だから、その他のことは任せた相手に委ねるというパターン。
一方で、②の場合。
こちらは事細かな指示があります。
Aの資料とBの資料、それに追加の資料をそれぞれホチキスで留める。
追加の資料は、表裏印刷で。
配布は、会議の前日の夕方まで。
配布するときに、「明日の会議の資料です。よろしくお願いします」と笑顔で伝える。
席にいない人にはメモ書きを添えて、机の目立つ位置に置く。
これら一つひとつ(過程)がどれも同じだけ大切で、どれもおろそかにはできないというパターン。
ですから、相手に委ねるという発想はありません。
自分が思う正しいやり方を、忠実に再現してもらいたい。
ですから、結果として、一つ一つの過程を事細かに指示することになる傾向があります。

さて、あなたはどちらのタイプですか?
そして、あなたのパートナーは?
察しのよい方はもうお気づきかもしれませんね。
そうです。
男性は、①の結果を重視。
そして、女性は②の過程を重視する傾向が高いのです。
たとえば、
- 妻:「子ども、見ててくれる?」
<私の思うやり方で> - 夫:「子ども、見てればいいんだね」
- 妻:「なんでただ見てるだけなの? 危ないじゃない! えっ!? もう面倒見るの終わり?」
- 妻:「お皿洗ってくれる?」
<私の思うやり方で> - 夫:「OK!」
- 妻:「水道出しっぱなしじゃないの! 洗剤だって付け過ぎだし…」
この過程を重視する女性特有の心理。
もっと言うと、相手のすることに、一つ一つ正しい(と本人が思っている)やり方を指示する心の傾向。
これを、<母性の門番>理論といいます。
カナダのカールトン大学リンダ・ダックスベリー(Linda Duxbury)博士や、「The Lazy Husband」の著者で心理学者のジョシュア・コールマン(Joshua Coleman)博士が提唱する理論です。
この<母性の門番>理論を家事に当てはめると、夫が、妻の行う通りに忠実に家事を行って、初めて手伝ったことになるということ。
ですから、いくら結果が同じ(洗濯物を取り入れる)でも、過程(たたみ方、しまい方など)が違えば、手伝ったことにはならない。
それどころか、むしろ、余計なこと扱いになるのです。
そして、<母性の門番>理論の及ぶ範囲は、洗濯の他にも、皿洗いの仕方、子どもの世話の仕方(どのように抱くか、どのような服を着せるか、どのように寝かしつけるか、etc.)、場合によっては野菜の切り方まで…。
無限にあるといってよいでしょう。
一方で、夫からすると、妻は家事を手伝ってほしいと要求しながら、そのやり方をいちいち指図してくると感じます。
まるで、門番のように。
こうして、妻の発言を「ダメ出しばかり」と感じ、いつの間にか家事をしなくなっていくのです。
いかがでしょうか。
ご理解いただけましたか?
「余計なことばかりする夫」「ダメ出しばかりする妻」のメカニズムが。
妻からすると、夫が余計なことばかりする。
それは、夫が男性心理(結果重視)の持ち主だから。
そして、妻がダメ出しばかりする理由。
それは、妻が女性心理(過程重視)の持ち主で、<母性の門番>理論を持つからなのです。
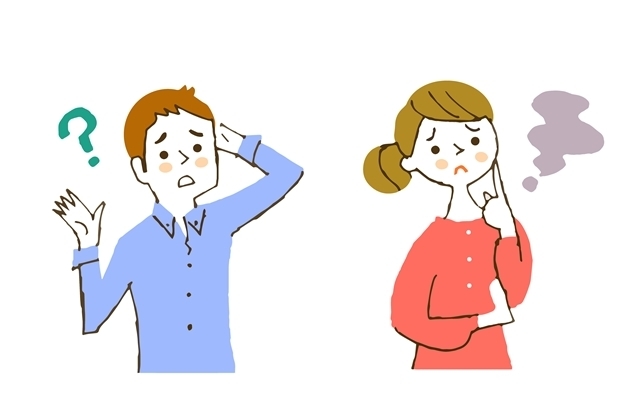
さて、話を我が家に戻しましょう。
どうして私の妻は、私が手伝ったときに心から喜んでくれるのか?
それは、私が妻のやり方を完璧にまねるからです。
洗濯物を干す場所も、洗濯物の取り込み方も完璧にまねます。
Tシャツのたたみ方、タオルのたたみ方、くつ下のまとめ方。
それぞれの収納先と収納の仕方。
普段から、妻のやり方を見て知っておくのです。
わからないときには、妻に(妻の正しい)やり方を教えてもらいます。
そうして、妻がするのと寸分違わぬやり方で手伝うのです。
(まるで奴隷のように感じますか? とんでもない。男性にとって最高に楽しくて、ワクワクする時間になります!)

つまり、妻にしてみると、私が手伝ったことで、やらなきゃなあと思っていたことが終わっているわけです。
それも、『まるで自分自身が行ったかのような状態で』(ここがポイント!)。
忙しいからなおのこと、妻は、こう思わずにはいられないでしょう。
「あぁ、助かる! ありがたいなあ。なんて優しい夫なのだろう」と。
だから、心からの喜びや感謝がわいてくるのです。
それも、自然と。
そして、そんな心から喜ぶ妻の表情や声が、私が家事を手伝うモチベーションとなって、再び妻を喜ばせることになります。
こうして、夫婦の関係に好循環が自然と起こってくるのです。
偉そうに書いてきましたが、もちろん私も最初から出来ていたわけではありません。
現に、二度も離婚していますし。
そんな私がどうして妻を喜ばせることができるようになったのか。
それは、私が女性心理を知ったからです。
今回でいえば、<母性の門番>理論のように。
そして、妻にも理解してもらう。
本当の男性心理を。
もちろん男性にだって、男性特有の心理があるわけですから。
つまり、夫か妻、どちらか一方ががんばるのではない。
お互いがお互いを大切にし、そして大切にされていると感じられること。
だから、好循環が生まれ、自然と愛が深まるのです。

あなたは、次のように感じること、あるいは感じたことはありませんか?
この人で、よいのか?
よかったのか?
私とこの人の「これから」は?
私は恋愛に不向きなのか?
私が幸せになる道は?
日本実践カウンセラー協会では、男女の恋愛心理、そして結婚心理が腹の底からわかる男女心理学講座を開催しています。
講座の内容は、下のリンクにより詳細をご覧いただけますが、簡単にご案内すると
https://www.j-pcpa.jp/kouza/danjo-renai
- 間違いのない結婚相手を選びたい未婚者
- 今度こそは幸せになりたい、離婚経験者
- 相手との距離感がどんどん大きくなってきた既婚者
- 今のところ順調だけど、もっと関係性を深め真のパートナー関係に到達したい方
老若男女問わず、男女の関係性をしっかりと学び、本当の幸せをつかみたい方向けの講座です。
この講座を受講することで、
自分の心が、なぜそのように動いたのか。
相手の心が、どうしてそのように動くのか。
異性の心、そしてご自身の心がわかります。
だからこそ、肩の力が抜け、根源的な幸せが見えてくることでしょう。
ご興味と関心のある方のお越しをお待ちしております。
執筆者:日本実践カウンセラー協会 高島昌彦
- 元航空自衛隊嘱託外部カウンセラー
- 元国立大学附属特別支援学校教諭
- カウンセリングMaNa 心理カウンセラー
教育学部にて自閉症を中心とする発達障害を専門に学び、大学卒業後は、国公立の特別支援学校教員として14年間勤務。
在職中に人間関係のストレスからうつ病を発症し、退職。
同じように苦しんでいる人の手助けをすべく、心理カウンセラーとして独立。
それと共に、自らうつ病を克服した際に用いた心理学、コミュニケーション学を応用し、独自の「必ず役に立つ、体感できる講座」を体系化する。
また、カウンセリング技術研修では、自らの経験から「苦しんでいる人が本当に必要としていること」を第一に、人の心の仕組みの深い理解、プロとしてあるべき意識の持ち方、そして必要不可欠な技術が網羅された、熱い中にも人間味のある講座を展開。
その人柄と他に例を見ない内容から、日本各地で絶大な人気を誇る。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
| 心 理 学 |
|---|
| N L P |
|---|